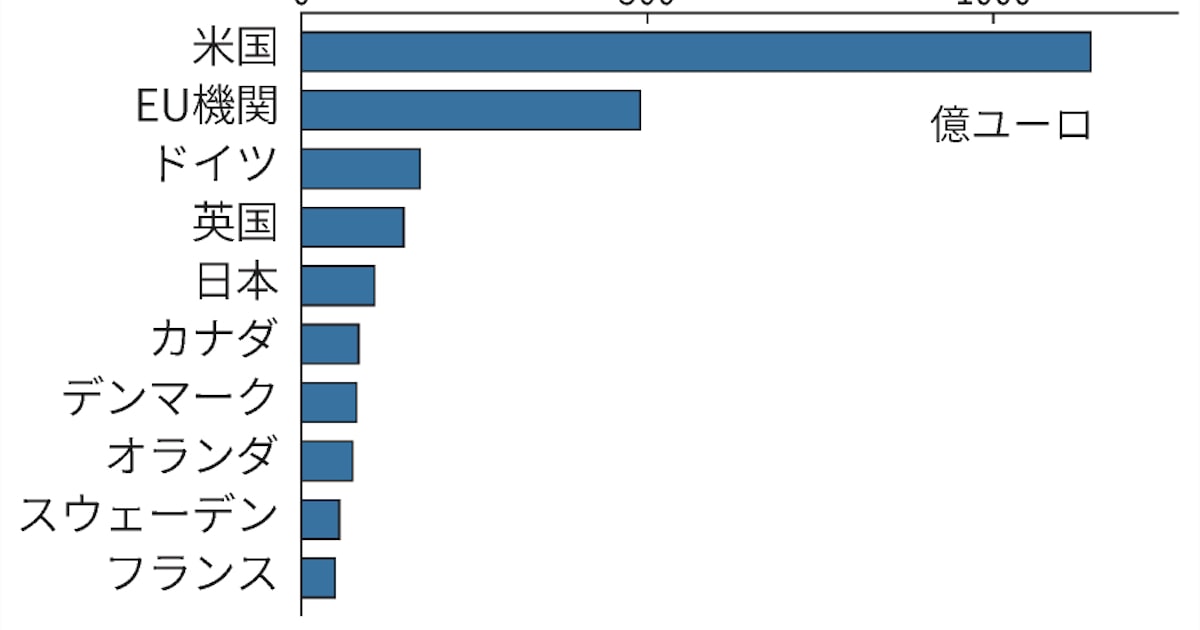トルコで行われていたウクライナ戦争の停戦交渉は結局まとまらなかった。その後、トランプ米大統領とプーチン露大統領が電話会談を行ったものの、やはり停戦合意には至らなかった。更に、トランプは停戦交渉の仲介を今後行わない意向を示した。
この停戦交渉決裂は見えていた。(補足1)ヨーロッパ諸国を背後に持つゼレンスキーがあまりにも傲慢であり、それは今年3月1日のホワイトハウスでの会見でも明確になっている。トランプの明確な決断が何を意味するかをこの戦争の真実を基礎に考えてみる。
以下は素人である筆者の想像も加えた文章であることを予めお断りしておきます。
1)ウクライナ戦争の真実と国務長官の発言
この戦争の真実は、ネオコン(隠れネオコン?)のマルコ・ルビオ国務長官が既に公言している。(補足2)つまり、ウクライナ戦争は、ウクライナを米国の代理とする米露間の戦争である。https://ameblo.jp/polymorph86/entry-12899323502.html
この米国務長官の言葉で重要なのは、米国はウクライナ戦争の当事国であることを認めたことである。一般に、戦争で負けた側は講和の際に領土を奪われ、賠償金を支払うなどの不利な条件で条約に調印しなければならない。その当事国が米国であると、米国外交のトップが公の電波の中で言ったのである。
代理戦争と明言したからには、ウクライナ国民の働きと犠牲など全ての負担に対してそれを埋め合わせる義務を米国は持つ。これまで米国が出した数十兆円以上を今後支出する覚悟も必要だろう。ゼレンスキーが傲慢な姿勢で米国に対するのは、このような論理を国務長官が認めたことが背後にある。
ロシアに完全勝利すれば、それらの債務や賠償の話が無くなると考えるのが、米国ネオコンたちと米国とともにウクライナ代理戦争を戦ったNATO諸国の首脳たちである。
その様に考えると、マルコ・ルビオ国務長官は完全なネオコンであり、トランプ政権を対露戦争に本格参戦させるか、トランプを早期に退陣させる意図でこのような発言をした筈である。これが3月15日に書いたブログ記事の内容である。
ここで、簡単にウクライナ戦争を復習する。ウクライナ戦争は、歴史的にはソ連崩壊に始まるロシアと米国との新冷戦に始まる。米国によるロシア弱体化あるいは分割(或いは分解)政策であり、この紛争は2014年から大きく報じられるようになった。そして、2022年2月から軍隊による直接戦闘となったのである。これは一貫して米国ネオコン政権のロシア潰し戦略であり、トランプはそれへの協力を否定してきた。
2014年とは、米国務省(ビクトリア・ヌーランドの活躍が著名)やCIA、そしてネオコンのバックにいるジョージソロスなどユダヤ系資本家がウクライナを内戦状態に導き、当時のウクライナ大統領のヤヌコビッチを国外に追い出した年である。所謂マイダン革命である。
マルコ・ルビオは、トランプ政権もこの代理戦争の当事国としてこの戦争を継承する義務があると公言したつもりかもしれないが、トランプには元々そんな気は無かった。繰り返すが、代理戦争をウクライナに発注し、その結果ウクライナ人が数百万人外国に避難し、百万人が家を失い命を失ったのなら、米国がウクライナに負う債務は膨大だろう。
更に、その戦争に負けたのなら、ロシアにも賠償金を支払う必要があるだろう。そんなことはできそうにない。トランプは、恐らくマルコ・ルビオを首にしたいだろう。ただもし首にしたら、背後のネオコンたちと釣るんで何を言い出すか分からないのでそうしないのだろう。
トランプの取り得る戦略としては、それは過去の米国の犯罪であり、新生米国の我々にはその責任全部は負いかねるという風に居直る作戦のみだろう。つまり、現在の米国は過去の米国から決別した新生米国であると主張する作戦ある。
ただ、プーチンならその白を切る作戦が通用するかもしれないと考えたとしたら、二人は人間を金や財産よりも大事にするキリスト教的道徳を残していると考えたているからだろう。
2)トランプの“新生米国を印象付ける戦略”は戦後ドイツがモデル?
このトランプの作戦は、2025年1月20日にこれまでの米国は終わり、自分の第二期政権から新しい米国が始まったとする姿勢を貫くことである。トランプは徹底的にこれまでのネオコン政治を否定するのは、これまでの米国の政治的遺産も債務も併せて放棄することの表明なのだろう。(補足3)
尚、米国ネオコン政権のこれまでの戦争については、コロンビア大学のジェフリー・サックス教授がヨーロッパ議会での演説において解説している。https://www.youtube.com/watch?v=hA9qmOIUYJA
要約すれば、ソ連崩壊後の東欧でのカラー革命(ウクライナのオレンジ革命を含む)、イラク、シリアを含む中東の戦争、スーダン、ソマリア、リビアを含むアフリカの戦争はすべてアメリカが主導して引き起こしたという悍ましい内容の話である。(補足4)
これだけの戦争を行う根拠は、米国による世界覇権の継続にある。この継続の延長上にグローバルエリートたちが密かに企む世界帝国の建設が存在する。その大きな目的がなければ、世界中から憎まれる侵略行為を続ける筈はないと考えるのが普通だろう。
トランプは、そんな残酷な世界戦争の果てに世界帝国を築いて何になると考えたのかもしれない。彼はこの企み(グローバリストの考える新世界秩序へのグレートリセット)に明確に反対する意思を示して来た。ただ、これまで政権内のネオコン勢力に足を引っ張られるように、彼らの主張にも一定の配慮を示してきたのである。しかし、ここで明確な仕切り直しをしたようだ。(補足5)
トランプは、このプーチンとの電話会談後の会見で、ウクライナ戦争に対する彼の政権の姿勢を覚悟を持って明確にし、それに念を押すかのように、今後のロシアと米国の経済協力の話にまで言及している。
このロシアとの経済協力の話だが、これには以下の意味があると思う。つまり、これまでのロシア潰しを世界戦略の一つとしてきたネオコン米国はもう存在しない。そこで新生米国はロシアとも新たな関係を築きたいという意思の表明である。
そんな勝手な理屈はあるかとロシア側には言いたい人が多いだろう。ただ、知的なプーチンなら報復に次ぐ報復ではいつまでたっても平和な世界は来ないと考えて、この作戦を受け入れてくれるだろうとトランプは考えたと思う。
この作戦のモデルは、戦後のドイツである。現ドイツはナチスを徹底的に批判し否定することで、過去の戦争に対し賠償要求する相手は今のドイツには居ないと主張している。それ故百歳に近いユダヤ人収容施設の門番も、探し出して無慈悲に刑務所に入れるのである。
終わりに
戦後ドイツの姿勢は、日本の戦後とは大きく異なる。来日したドイツのメルケル首相が安倍総理に進言したのもこの“しらを切る作戦”(或いは内外に過去と決別を印象づける戦術)だと思われる。(補足6)その意味を日本人は理解しなかった。
つまり、過去の日本を徹底的に批判し新生日本を明確にすることで、中国や半島からの戦争責任論とその背後に控える将来の戦争や賠償要求を封じる戦略である。しかしそれは現状の日本には相当難しい。現在の天皇制を維持する限り無理であるが、それを克服することは可能である。
過去何度も書いているが、日本の天皇と伊勢神道は明治の富国強兵策の中で利用された。その天皇の面影が政治の中に残る限り、新生日本の演出は無理である。例えば、戦後没収された天皇家の財産を一定程度返却して、江戸時代までのように京都に皇居を移し、伊勢神道のトップとなって日本国民との関係を元に戻すという考え方はないだろうか?
このまま米国が東アジアから手を引けば、日本は中国の支配下にはいる可能性が極めて高いと思う。何もしなければ、武家(国家公務員や政治家)が中国人で町人が日本人のような江戸時代の社会構成が、再び日本を支配するようになる可能性がある。
また、米国がネオコン支配のままなら、今のウクライナのように米国の潜在的敵国である中国潰しのために代理戦争を強いられ、数百万人が命を落とすことになるかもしれない。このまま日本人が政治音痴を続ければ、それら何れかの恐怖が日本を襲う時が来る可能性が高い。
補足
1)クリミヤまでも返せというゼレンスキーの姿勢は無知なのか馬鹿なのか? シカゴ大のミアシャイマー教授はヤケクソだと言っているようだが。。。https://www.youtube.com/watch?v=uQaMnOrKrIo
2)最初この話を聞いたとき、信じられなかった。何故なら、ウクライナを代理にして米国がロシアと戦争していることは本来の保守側には常識だが、それを言えばグローバリスト・ネオコン側から陰謀論のレッテルを貼られて、現在のポジションから放り出される可能性が高いからである。マルコ・ルビオがそれを言っても断罪されないのは、その背後にトランプをウクライナ戦争に巻き込むためという了解がネオコン側にあるからだろう。トランプは、マルコ・ルビオを抱き込んだのは兎に角政権を作り上げるためだろう。
3)ここでの義務や債務などの話は法的な話ではない。国際関係は野生の原則が支配するので、法治の原則からは程遠い世界である。しかし、歴史を動かすのは人間の感覚であり、それはこれら法的用語を用いることでより詳細に記述可能となる。
4)この動画での講演内容は、長周新聞により日本語に翻訳されているので、私は主にそちらで読んだ。https://www.chosyu-journal.jp/kokusai/34317
https://www.chosyu-journal.jp/kokusai/34414
5)ここで5月2日の記事でトランプは単なるポピュリストであると書いたのは間違いであり訂正させていただく。https://ameblo.jp/polymorph86/entry-12899323502.html
6)過去の記憶で書いているので、この理解だけでは不十分かもしれない。また文献は存在するが、その思想を日本に具現化する方法とその可能性などについては触れられていない。以下の文献については評価していないが、一応今後の思考のために引用のみしておく。
(11:40 改題)